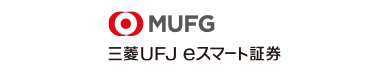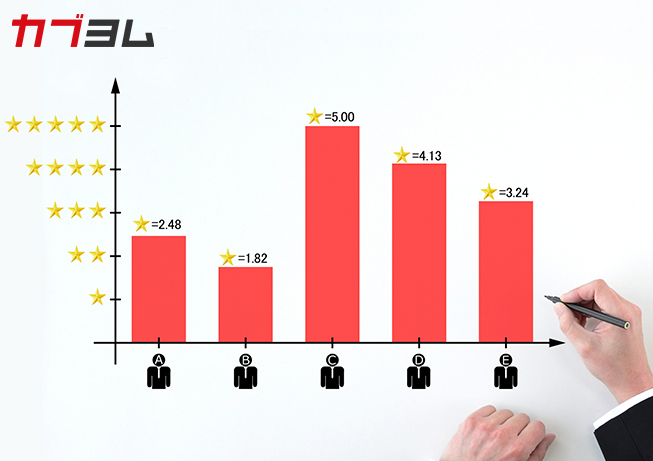執筆者:カブヨム編集部
投資は現在、多くの人にとって身近な存在となっています。しかし、実際に何歳ごろから投資を始めるべきか迷っている方もいらっしゃるでしょう。また、お子さんのいるご家庭では、どうやって子供のための資産運用を行うか、またどのように未成年のうちから金融教育を行うべきか悩む場合もあるでしょう。
この記事では、投資を始める年齢や、未成年者本人の名義で保有できる口座についてご案内します。
投資を始める年齢について
投資を始める年齢には、明確な正解はありません。当然のことですが、個々の状況や目的によって異なるからです。しかし、早期の投資開始は時間を味方にできるため、資産形成において有利に働きやすいと言えるでしょう。ここでは、異なる年齢における投資の利点や考慮すべきポイントについて詳しく解説します。
投資の早期開始のメリットとは
投資を早くから開始することで、次のような恩恵を得やすくなると言えます。
1. 複利効果:
投資元本に対して生じた利子や配当金が再投資されることで、元本が次第に増加し、その増加分に対してさらに利息や配当が付くという「複利」の効果を享受できます。この効果は時間が経つほど大きくなり、長期間にわたって投資することが資産形成において有利に働きます。
2. リスクの分散と長期的視野:
長期にわたる投資は、市場の変動によるリスクを平準化する効果があります。短期的な市場の変動に左右されず、より長期的な成長を見込んで投資を続けることで、リスクを軽減しながら資産を増やすことが可能です。
3. 投資経験の蓄積と学び:
若いうちに投資を始めることで、より様々な相場や投資判断の経験を積むことができます。また、若いうちは比較的、リスクを許容しながら利益を狙うという投資スタイルを取りやすいという点も特徴でしょう。投資に「絶対」はないとはいえ、失敗しやすい相場を学んだり、自分の投資判断を振り返ったりするチャンスが増える分、先々の判断に役立つこともあるかもしれません。
年齢別の投資戦略、どんなものが考えられる?
年齢によって適した投資戦略は変わります。ライフステージに応じた投資方法を選択することが、資産形成の成功につながります。
- 10代:資産形成の基盤づくり
10代から投資をする機会に恵まれている場合、資産形成の基盤を築く時期です。まだ投資に回せる資金が十分ではないこの年代では、基本的な金融知識を身につけ、将来に向けた長期投資の重要性を学ぶことが推奨されます。実践の上では、例えば、少額から投資信託のつみたてを始めてみたり、比較的価格を抑えて購入できる単元未満株(100株未満の株式)を購入してみるなど、コツコツと投資の一歩を踏み出すことが望ましいでしょう。 - 20代: 比較的アグレッシブな投資が可能に
就職して自分自身の収入を得られる方が増えるこの年代は、比較的リスク許容度が高く、株式等への積極的な投資を始めやすい年齢です。安定型の資産だけでなく、成長企業への投資や、新興市場への投資を検討することで、より大きなリターンを目指すことができます。もちろん、リターンを取りやすい分リスクも伴うため、十分な情報を基にした投資判断が必要となります。 - 30代~40代: バランスの取れた資産配分
資産のバランスを考え始める非常に重要な時期です。特に家庭をお持ちの方は、ご家族の将来を踏まえたライフプランを検討する必要があるでしょう。そのためこの年代では、株式等の比較的リスクの高い資産だけでなく、固定収入型の債券を組み合わせるなど、資産全体の安定性を持たせると良いでしょう。 - 50代~: 安全資産へのシフト
退職後の生活が見え始めるこのころは、一般的にリスクを抑えた資産配分が求められることが多いです。このタイミングで、安全資産へのシフトや、リスクヘッジ戦略を強化することが重要です。具体的には、安定した利益を期待できる債券や、マーケットの変動に強い資産への投資を検討すると良いでしょう。
もちろん、ここに挙げた例はあくまで参考例です。実際には個々の状況に応じて投資戦略は変わるため、ライフプランを見据えて定期的に方針を見直すことが重要です。
ジュニアNISAは廃止に!代わりに子供が投資を始める方法は
ここまで、なるべく若いうちから資産形成に着手するのがおすすめであるとお話してきましたが、将来を見据えた長期的な資産運用に適した制度と言えば、「NISA口座」が思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。NISAは投資で得た利益を非課税で受け取れるという便利な制度で、原則18歳以上の方がNISA口座を開設できます。
ですが実は、2023年までは、未成年を対象とした「ジュニアNISA」の制度も存在していました。
ジュニアNISAは、親や祖父母が未成年者のために金融商品に投資することを促進するために設けられ、未成年の資産形成を助ける役割を果たしていましたが、残念ながら2023年の旧NISA制度とともに廃止となりました。
※2023年までに開設したジュニアNISA口座で保有していた商品については、非課税期間(5年)終了後、自動的に継続管理勘定に移管され、18歳になるまで非課税で保有することが可能です。
ジュニアNISA廃止の背景
ジュニアNISAは、利用者数の伸び悩みや制度の複雑さが問題視され、廃止に至りました。この背景には、親権者の理解不足や、不十分な投資教育の影響があると考えられています。また、複雑な手続きと資金拘束のルールが一般家庭にとって敷居を高くしていたことも一因ではないかと推測されます。
ジュニアNISA廃止を受けた「代わり」の方法
ジュニアNISAが廃止され、未成年のための資産運用が模索されています。2025年4月時点での主な選択肢としては、親権者名義の証券口座(NISA口座)で子供のために資産運用をする方法や、未成年口座を活用した投資が考えられるでしょう。
まず親権者名義の証券口座(NISA口座)を活用する方法では、親が代わりに投資を行い、その運用益を将来的に子供のために使うということが考えられます。一般の証券口座(NISA口座)は基本的に、18歳以上の成人しか開設できないため、未成年が自分の名義の口座を持つことはできません。あくまで親権者名義での運用となります。運用益を将来的に子供に譲渡する場合は、贈与税がかかってくる可能性もある点は留意しておきましょう。
一方、未成年口座では、子供本人の名義で証券口座を作ることができる点がポイントです。将来的に成人した後は、そのまま本人の成人用証券口座に変更となります。
未成年口座とは?特徴を解説
証券口座における未成年口座とは、未成年者が親や保護者の同意のもとで開設できる証券口座です。
なお銀行口座においても同様に、親や保護者の同意のもとで未成年口座を開設することができますが、ここでは証券口座としての未成年口座についてお伝えしていきます。
未成年口座について整理すると、次のような特徴があります。
<証券会社の未成年口座における一般的な特徴について>
| 項目 | 詳細 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 投資可能額 | 年間の投資上限なし | 運用資金を親権者から子へ贈与する場合、贈与税の非課税枠である年間110万円を超えると贈与税がかかります(*1)。 |
| 取引・管理を行う主体 | 親権者 | 名義人が成人した後は、親権者が自由に資金を引き出すことはできません。 |
| 投資可能な商品 | 株式・投資信託・債券など | 一般に未成年口座では、信用取引やFX取引等の比較的リスクの高い商品は取引できません。 |
| 利用目的の例 | 株主優待やIPO投資、贈与税対策など | - |
*1:未成年口座への資金贈与においては、贈与契約書の作成や、年間110万円を超える場合の贈与税申告・納税が発生する点に留意が必要です。贈与契約が曖昧な場合は「名義預金」とみなされるケースもあります。贈与等の詳細については必ず最新の情報をご確認ください。
※上の表は当社で作成。利用目的などはあくまで参考例となります。
※実際の未成年口座の開設にあたっては、必ず証券会社の規定をご確認ください。
なお、証券会社によって、未成年口座の開設には特定の書類を求められる場合がありますので、事前に確認しておくことが重要でしょう。
未成年口座開設のメリット
未成年の投資口座にはいくつかの大きなメリットがあります。
第一に、早期の資産形成が可能です。子供が若いうちから資産形成に着手することで、将来的には学費や結婚資金など、さまざまな費用に備えることができます。時間を味方につけて投資を行うことで、将来の経済的な選択肢が広がり、より安定した生活を送るための基盤を築くことができるでしょう。
次に、金融教育の機会を得られることが挙げられます。早くから子供名義の口座を持つことで、資産運用や投資への理解が得られやすくなります。そして資産運用の傍ら、投資のリスクなどの基本概念を学ぶことで、将来的に子ども自身で資産形成を行うための知識が養われていくことが期待されます。
また、親子間のコミュニケーションの深化も大切なポイントです。家庭内で健全にお金に関する話ができることで、価値観の共有や理解を促進する良い機会となります。その結果、将来的な金融教育の機会につながったり、健全な金銭感覚を育んだりすることができるなど、子供にとっても有意義な学びとなり得るでしょう。
未成年口座開設の注意点
しかし、未成年口座での投資を行う際には、いくつかの注意点もあります。
まず、口座開設にあたって親権者の投資への理解と協力は不可欠です。名義は子供のものであっても、未成年口座においては原則親権者が資産運用・管理を行うことになるため、親権者自身が投資に関する基本的な知識をしっかりと保有していることが大切です。また、未成年口座の開設にあたっては、親権者自身の証券口座も必要です。
さらに、リスク管理の重要性についても強調したいと思います。名義人が未成年であっても、投資を行う以上元本割れを起こすリスクはあります。「必ず儲かる」という性質のものではありませんので、取引のリスクについて理解のうえで、投資先についてよく検討する必要があります。 未成年口座で取引できる商品は、株式・投資信託・債券など、成年口座とあまり変わりません。ただし一般的に、比較的投資リスクの大きな信用取引・FX取引などは行えません。
また、事前に贈与契約書を作成しておくことで、未成年口座に入金する資金は贈与扱いとなりますが、贈与税非課税枠の年間110万円を超えると贈与税が発生します。
贈与と合わせて注意したいのが、未成年口座での売却益です。未成年者の年間所得が一定額を超えると、基礎控除が受けられなくなる可能性があります。
最後に、未成年口座の名義人が18歳を迎えて成人した場合についてです。未成年者が成人すると、口座は成人用の証券口座に移行します。未成年口座の場合は親権者が管理をするのが一般的ですが、成人用の証券口座に移行した後は親権者が勝手に引き出すことはできなくなり、本人の委任状が必要です。
まとめ
投資を始める年齢には、明確な正解はありませんが、早期に始めることで多くの利点を享受できる可能性が高まります。
ただし、成功には十分な知識と計画性が求められます。できるだけ投資する目標を明確にし、リスク許容度に応じた投資計画を立てたうえで、必要に応じて戦略を見直すことが大切です。
また、実際に過去にジュニアNISAが廃止になったことなどからもわかるように、投資に関する制度は様々な事情から変化することがあります。常に最新の情報をキャッチして、投資環境に適応できるように意識を向けさせるという点も、ひとつの金融教育の形と言えるのではないでしょうか。
ぜひ、ご家庭での金融教育を検討しつつ、早いうちから資産形成の意識を身に着けられるよう、未成年口座の活用を検討してみてください。