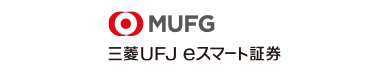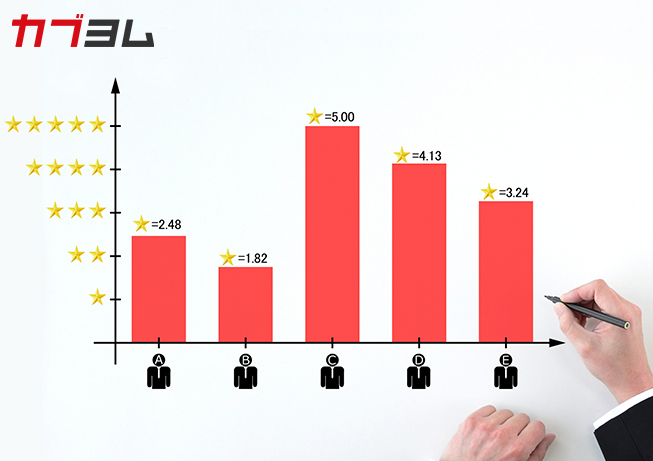イールドカーブとはどんなもの?
「イールドカーブ」という言葉を、目や耳にされたことはありますか?
イールドカーブとは、債券の残存期間(満期までの期間)と利回りの関係をグラフ化したもので、市場や景況を見通すときに役立ちます。イールドは利回り、カーブは曲線を表す言葉で、日本語で「利回り曲線」と表されます。
イールドカーブは、1種類の債券ではなく、同種類の債券の中で残存期間が異なる複数の債券の利回りをグラフ化しています。つまり、イールドカーブは特定の債券の利回りの動きではなく、市場全体の動きを表しています。
イールドカーブの形状と傾きは何を表しているの?
イールドカーブの形状にはそれぞれ、「順イールド」と「逆イールド」と呼ばれるものがあります。
順イールドとは
順イールドとは、イールドカーブが右肩上がりの状態です。満期までの期間が長い債券ほど、利回りが高くなる状況を示しています。投資家が将来の経済成長に期待し、長期投資のリスクに応じた高いリターンを求める心理や行動が反映されています。一般的には、順イールドは好況を示すサインといわれています。
逆イールドとは
逆イールドは、右肩下がりの状態です。短期債券(満期までの期間が短い債券)の利回りが、長期債券(満期までの期間が長い債券)の利回りを上回る状況を示しています。投資家が将来の景気が後退することを予測して、安全な長期債券に資金移動させる心理や行動が反映されています。一般的に逆イールドは、景気後退局面の先行指標といわれています。
またイールドカーブの傾きを表す「フラット化」と「スティープ化」という用語について、それぞれご説明します。
イールドカーブのフラット化とは
イールドカーブのフラット化とは、イールドカーブの傾きが緩やかになる状況です。この状況は、短期金利と長期金利の差が縮まることで発生します。イールドカーブのフラット化は、市場が将来の経済成長スピードの鈍化やインフレ抑制を予測している状態を示しています。つまりイールドカーブのフラット化は、景気後退局面を示す逆イールドのサインとなり得ると考えておくとよいでしょう。
イールドカーブのスティープ化とは
イールドカーブのスティープ化とは、イールドカーブの傾きが急になる状況をいいます。この状況は、短期金利と長期金利の差が拡大することで発生します。イールドカーブのスティープ化は、将来の経済成長やインフレへの期待が高まり、長期金利が上昇することによって起こります。イールドカーブのスティープ化は、景気回復の初期段階や、金融緩和政策が実施された際に起こる傾向があります。
<イールドカーブの形状と傾きのイメージ>

※画像は筆者が作成
逆イールドはなぜ起こる?投資への影響は?
イールドカーブの形状のうち、「逆イールド」は景気後退を示すサインです。景気が後退すると、株価下落といった投資への影響のみならず、勤務先の業績不振や消費控えなど生活にも影響が生じる可能性もあります。そのため、どんな要因で逆イールドが生じるのか気になる方も多いのではないでしょうか?
逆イールドが起こる要因には「金融政策」と「投資家の予測」が挙げられます。
<逆イールドが起こるイメージ>

※画像は筆者が作成
要因その1:金融政策
金融政策により、逆イールドが発生する場合があります。例えば、中央銀行が景況過熱を抑制するため、短期金利を大幅に引き上げることがあります。短期金利が引き上げられると、短期債券の利回りは上昇します。一方で、将来の景気悪化を予測する動きも同時に現われます。景気が悪化すれば企業の設備投資や新規事業のほか、個人の住宅ローンなどの資金需要が低下すると考えられるため、長期金利は上がりにくくなります。その結果、短期債券の利回りが長期債券の利回りを上回る逆イールドが発生します。
要因その2:投資家の予測
投資家の予測が逆イールドを発生させる場合があります。将来の景気後退を予測する投資家が多くなると、短期債券よりも比較的安全な資産と考えられている長期債券への需要が高まります。長期債券の需要が高まれば債券価格は上昇し、利回りは低下します。その結果、短期債券の利回りが長期債券の利回りを上回る逆イールドが発生します。
逆イールドは投資にどのような影響を与えるの?
逆イールドは、景気後退局面の先行指標です。そのため、逆イールドが発生すると、企業の業績悪化、株価下落が懸念され、株式を売却する動きが強まる場合があります。中でも製造業や建設業など、景気変動に敏感な業種の株価は大きく下落する可能性が考えられます。また、株価上昇が見込めない状況において、投資家は債券投資を増やす動きへとシフトする可能性があります。債券需要が高まれば、債券の価格が上昇するため利回り低下が起こりやすくなります。
日本のイールドカーブコントロール(YCC)とは?
かつて日本には、日本銀行がイールドカーブを意図的に操作する金融政策がありました。その金融政策とはイールドカーブコントロール(以下、YCC)で、景気刺激と物価安定を目的として2016年に導入されました。具体的には、短期金利を低く抑え、長期金利を一定水準に誘導するために日本銀行が国債を大量に購入して実施されました。2024年3月には、金融政策の目的を安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったとしてYCCは解除されました。
YCCの実施により、企業は資金調達コストを抑制できるため、設備投資を行いやすくなり景気が活性化する可能性が高まります。YCCは長期金利を一定水準に抑えるように慎重に実施されるため、緩やかな景気回復および物価上昇となり物価も安定しやすい状態になることが見込まれます。
このように、金利が低くなることで、企業や個人は資金調達が容易になるメリットがあります。ただし一方で日本銀行が国債を大量に購入し、意図的に価格を操作することになるため、国債の本来の需給バランスが不明確になり、投資判断が困難になるデメリットもあるといえるでしょう。
イールドカーブを理解して投資戦略を考えよう
2022年以降、アメリカのFRB(連邦準備制度理事会)は、高インフレ過熱を抑制するため、急速な利上げを実施しました。その結果、インフレは抑制されましたが逆イールドが発生し、大きな景気後退が懸念される場面もありました。
このほか、2000年代の初めにもITバブルの崩壊やリーマンショックの前に、逆イールドが発生しています。その後、景気後退が生じたことはご存じの方も多いでしょう。
逆イールドの発生は事例からも分かるように、将来の景気悪化を示すサインとなり得ます。投資情報提供サイトや一部の証券会社でイールドカーブの状況を確認できますので、検索してみてください。
逆イールドの発生があったときには、資産状況を確認し、株式などのリスク資産の比率を減らし、債券や預貯金などの安全資産の比率を高めることを検討するのもよいでしょう。
ただし、逆イールドが生じてもすぐに株価が下落するとは限りません。大切なのは、経済動向や金融政策の発表に注目し、冷静に判断することです。また、万が一に備え、普段から株や債券など、さまざまな金融商品に分散投資しておくと慌てず対応ができるでしょう。
また、逆イールドは、ピンチであると同時にチャンスと捉えることもできるでしょう。例えば、長期債券の価格上昇、割安な優良株式銘柄を狙った投資を行うチャンスとなるかもしれません。
イールドカーブを賢く投資に活用するためにも、自分の投資状況の確認とイールドカーブへの正しい理解に努めましょう。逆イールドの発生時だけでなく、日ごろから投資戦略を練り、慌てずに慎重に行動するように心がけることが大切です。